エアコンなしでも大丈夫!熱中症を防ぐ暮らしの工夫
はじめに
夏の暑さが30度を超える日々が続き本格化しています。
気づけば、今日は熱中症で何人運ばれたというニュースを聞かなかった日はありません。
そんな中、「我が家はエアコンがないから…」と不安になる方も多いかと思います。
さらに、精神障害のある方と暮らしている家庭では、体温調節や体調の変化に気づきにくいなど、熱中症のリスクが高まることもあるのです。
ここでは、エアコンがなくても実践できる熱中症予防の工夫に加え、
精神障害のある方への配慮と支援のヒントも紹介します。
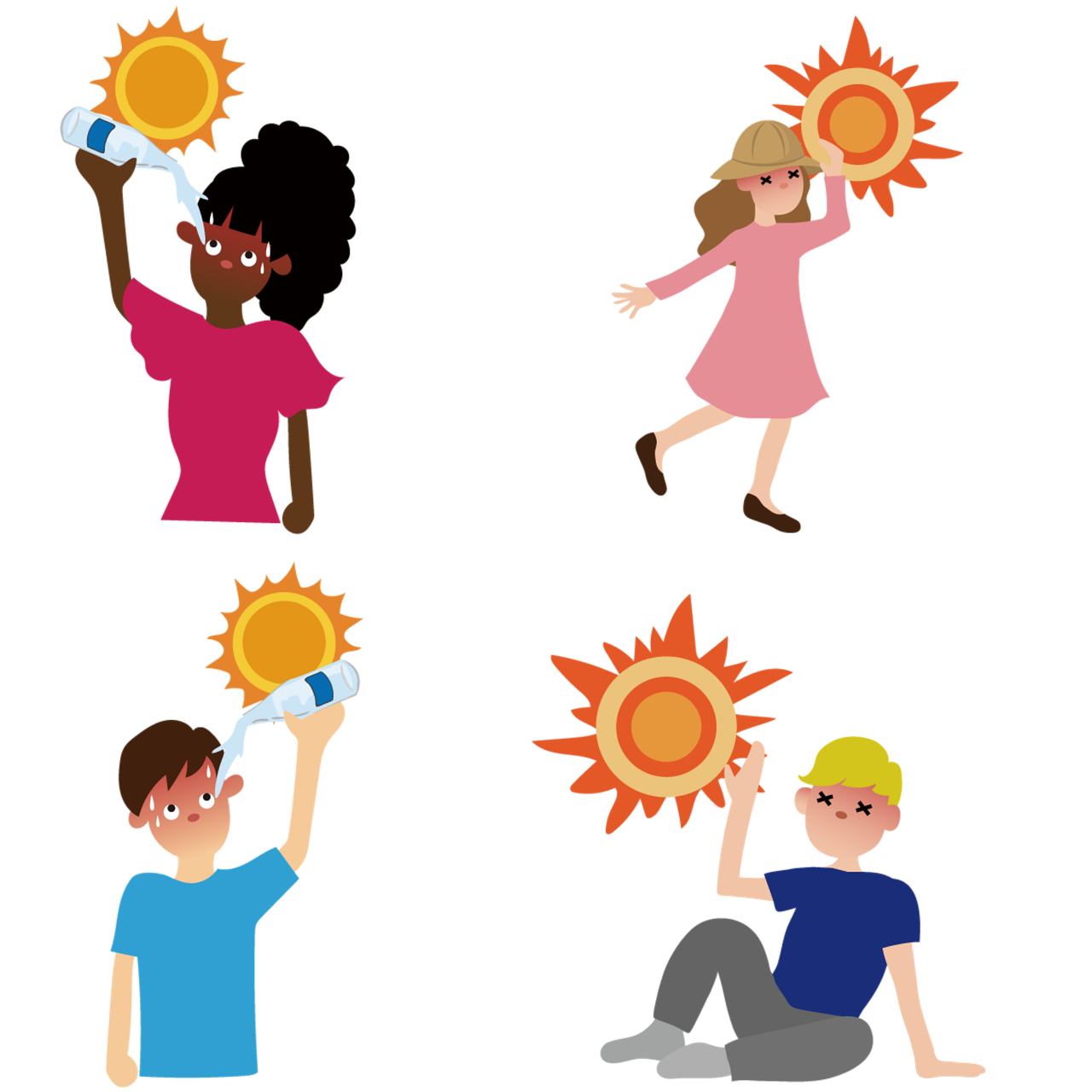
なぜ精神障害のある方は熱中症になりやすいのか?
・体温調節が苦手:服薬の影響で汗が出にくく、体に熱がこもりやすい。
・暑さや渇きに気づきにくい:集中力や感覚の変化により、体調の異変に気づきにくい。
・意思表示が難しいことも:「暑い」「苦しい」と言えない場合があるため、周囲の気づきが重要。
暮らしの工夫で涼しさをつくる
・扇風機やサーキュレーターなどを上向きにして風を循環させる。
・朝晩の涼しい時間帯に換気する。
・すだれや遮熱カーテンで日差しを遮る。
・打ち水で外壁やベランダに水をまくことで気化熱を利用し、室温を下げます。
・風の通り道を確保して窓を対角線上に開け、扇風機などで空気を循環させます。
・保冷剤や冷凍ペットボトルを扇風機の前に置くと、冷風のような感覚になります。
・冷感寝具・ジェルマット・クールネックリングなどを使うと、体温を直接下げる効果があります。
精神障害のある方への声かけと見守り
・「お水飲んだ?」「暑くない?」など、やさしい声かけをこまめに。
・「ここに座ると少し涼しいよ」「冷たいタオル使ってみようか」など、肯定的で安心感のある言葉を使いましょう。
・「こっちとあっち、どっちが気持ちいい?」と本人の感覚を尊重しましょう。
・表情や動きの変化に気づいたら、すぐに休ませる。
・水分補給のタイミングを一緒に決める(例:1時間ごとに一口飲む)。
・チェックリストやタイマーを活用して、水分補給の習慣化をサポートする。
水分補給の工夫
・無糖の麦茶や水を基本にする。
・飲みやすい容器や、好みの飲み物(無糖麦茶など)を用意して、自発的に飲める環境を整えましょう。
・経口補水液は体調が悪いときに限定して使用する。
・甘い飲み物の過剰摂取は「ペットボトル症候群」のリスクもあるので注意する。
※ペットボトル症候群:糖分の多い清涼飲料水(ジュース・スポーツドリンクなど)を大量に飲み続けることで起こる急性の高血糖状態のこと。
支援者・家族ができること
・室温・湿度の管理(温湿度計を活用)する。
・涼しい場所へ誘導する。
・水分・塩分の“質と量”のバランス確認する。
※質と量のバランス確認:“何をどれだけ、いつ取るか”を見守ること。
特に精神障害のある方や高齢者は、体調の変化に気づきにくいため、周囲の支援が命を守る力になります。
・外出時は「お出かけ前チェックシート」で忘れ物などを防止する。
暑さを乗り越える“共に暮らす知恵”
精神障害のある方と暮らす日々は、時に予測が難しいこともあります。
でも小さな気づきと声かけ、そして一緒に工夫する姿勢が、安心と安全につながるんです。
「エアコンがないからこそ知恵と、つながりで乗り越える」
そんな暮らしのヒントが、誰かの夏を守る力になることを願っています。
今年の夏も、皆さんが安心して安全で過ごせますように…